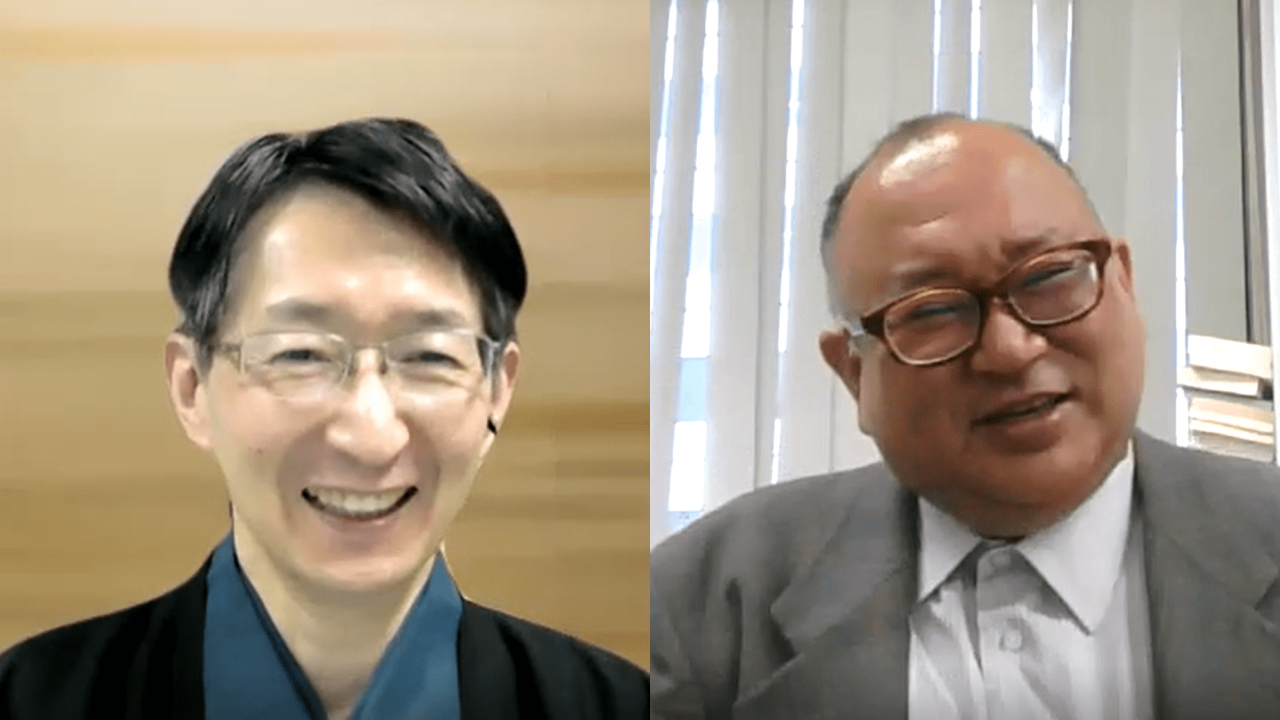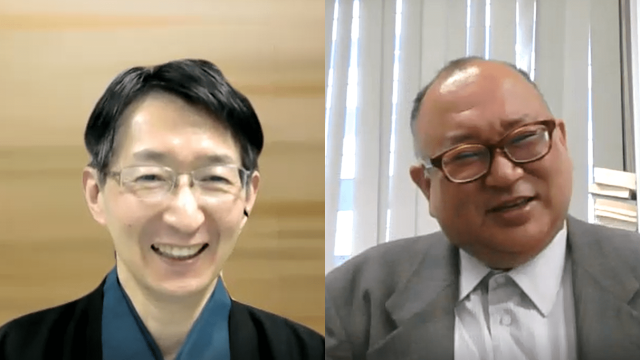本対談では、2022年2月に出版した『お茶と権力 信長・利休・秀吉』(発行元:文春新書、価格:935円)」をテーマに、その読みどころについて、両者の視点から語っていただきました。本対談は、前編、中編、後編の3篇に分けてお届けします。
田中仙堂プロファイル(写真:左)
1988年、円覚寺前管長より仙堂の号を享け、同年大日本茶道学会副会長、2017年1月に同会会長に就任。創始者田中仙樵、父仙翁会長の意を継いで、茶道文化が伝えてきた「わざ」と「こころ」の両輪に価値をおき、点前の実践に加えて、論考でも日本の伝統文化を紹介している。月刊「茶道の研究」を主宰。著書に『近代茶道の歴社会学』(思文閣出版社)、『茶の湯名言集』(角川ソフィア文庫)、『岡倉天心「茶の本」を読む』(講談社)、共編緒に『講座 日本茶の湯全史 第三巻 近代』(思閣出版)、『秀吉の智略「北野大茶湯」大検証』(共著淡交社)、『茶道文化論 茶道学大系 第一巻』(淡交社)など多数。
1958年、東京都生まれ。本名 田中秀隆(ひでたか)。東京大学文学部社会学科卒業後、東京大学社会学研究科博士課程単位取得(満期退学)。カナダ政府給付留学生としてケベック州ラバル大学大学院に留学。
前島編集長プロファイル(写真:右)
1969年、岐阜県生まれ。1992年、東京大学文学部社会学科卒業。同年、文藝春秋に入社。「週刊文春」、月刊誌「文藝春秋」、「諸君!」、「文藝春秋スペシャル」などの編集部を経て、現在、文春新書編集長。
パフォーマンスとしての黄金の茶室

前島: もともとお茶の文化というのは、武家の文化なのですね。
田中: 鎌倉時代に、今日のお茶につながる宋の時代の点茶法が入ってきてから、お茶は、産地を飲み分けるゲームとして流行します。それは、「闘茶」といわれ、建武の新政の頃には、一種の賭け事として禁止令が出されるほど目につき流行ったようです。公家たちの闘茶と武家の闘茶の記録を比べると、両者の財力の差を感じます。バサラ大名として有名な佐々木道誉などは、金銀、唐物、砂金等、様々なものを山ほど、闘茶の掛けものに出してくるのです。どうだ俺は、こんなすごいものをもっているんだぞ、と自慢しあう側面があったために流行ったのでしょう。そして、持っているものを自慢するにしても、金銀をそのまま見せびらかすのでなく、より入手不可能なものを持っていた方が、評価されるということになっていった。他人と比べて自分を評価してもらいたいという気持ちは、力をつけてきた武士たちの方に強かったと思いますし、自慢するためのツールというルーツを茶道具の世界も持っていたわけです。
前島: すると、茶道具の文化は武家の世界では発展して共有されてくるけれども、公家にとってはそれほどではないということになるわけですね。そこで、茶道具の文化をそれほど共有していない公家を圧倒するためのパフォーマンスとして、秀吉は黄金の茶室を用意する。実際それは、公家たちの心をつかむわけですね。
田中: そうです。あと、黄金の茶室のもう一つの効果として、宮中に持ち込むために、組み立て式にしたことによって、宮中での献茶の後にも、秀吉は様々な人に見せびらかすことができるようになるのです。北野大茶湯という北野神社で行ったパフォーマンスでも、黄金の茶室が飾られています。それは、秀吉にとっては、黄金の茶室を参加者に見せて、「おれは宮中で献茶をやったぞ」ということを周りの人に知らしめる意味があったのだと思います。ニュースのない時代では、宮中で献茶があったとしてもそれを知る人はごく限られていますから、秀吉は広く知らしめたいと思ったのではないでしょうか。
前島: 当時は、ウェブがあったりするわけではないですから。その黄金の茶室を見せることが、ある意味、自分たちが宮中で茶会を開いたという大宣伝になる、という訳ですね。
田中: これを作ったのは宮中で献茶をするためだと説明をすると、秀吉が宮中で献茶をしたことを相手が知るという具合です。
前島: 大阪万博で展示された「月の石」のようなものですか。先ほど以来、戦国武将のパフォーマー論と非常にぴったり重なり合う、やっぱり秀吉はパフォーマーとして、お茶を実はよく理解していたのではないかという見方ですね。そういう意味では、信長、秀吉、利休の3人それぞれの像もずいぶん変わって見えてくると思いました。
田中: そういっていただけるとうれしいです。もちろん私の発想の元をたどれば、一般的な秀吉像が背景にあるわけで、黄金の茶室を持ち出して公家たちに示してというのは、言ってみれば「鳴かぬなら鳴かせてみましょう」という秀吉のイメージが自分の中にあるので、それを膨らませて推測できたのではないかと思います。
前島: この本で描かれる秀吉は希代のパフォーマーといいますか、一代で天下を取る創意工夫に結び付いている印象を受けました。
田中: そうです。戦国大名が成り上がったといいますが、室町幕府ができたときからの守護大名家ではないけれども、その下の名家の人間みたいな人々が、織田家とか朝倉家であったわけで、成り上がるといっても、秀吉の成り上がり方とは比べ物にならないと思います。秀吉が乗り越えなければならない壁は、他の戦国大名と比べてとてつもなく大きかったと思います。
利休はなぜ重用されたのか?
前島: では、次は利休についてうかがいたいと思います。田中さんは、利休については長く研究されておられるかと思いますが、本書を書く上で気をつけられたことはなんですか。
田中: 私達茶人の側から言うと、利休がなぜ重用されたのか、の答えは、「利休が立派だから、利休の茶が素晴らしいからです」ということになります。私はそれに組みしたい気持ちはあるのですが、意識的にそれ以外の答えを考えなければならない思っています。原因を利休の資質にするとそこで問いかけが止まってしまいますからね。また、その時代が身分社会であると考えると、当時の為政者と一介の茶人とどちらが偉かったのか、という視点で考えてみました。同時代の人がどう受け止めたのかということを想像するしかないわけですが、それが何かと想像して考えてみるのも歴史的アプローチの一つなのではないかと思っています。
前島: あえて利休を信長や秀吉という軸から見ることで、戦国のお茶のリアルを描いてみたということですね。
田中: はい。それに、利休の偉さとは、分かる人にはわかるようですが、どれだけの人が理解したのか、疑問が残ります。これは、例えば我々が何か今の時代の立派な芸術家だとか文化人と言われている人のことを、どれぐらいわかるかというように考えれば分かると思います。何か立派な賞を取った、首相官邸に出入りしているとか、そんな風にしか分かっていないことも多いですよ。
前島: 秀吉が、単なる信長の後継というだけではなく、利休を重用していくのは、やはり、秀吉からみた利休のパフォーマンスの評価なのでしょうか。
田中: そうですね。ただそのパフォーマンスは、茶人という枠を超えてまで秀吉に付き合ってしまったのかという気がします。
前島: なるほど。利休のパフォーマーとしての広がりが茶人を越えてしまった、ということですか?
田中: 利休は「私は茶人だから、この戦いの仲介ですとか、どっちがどうですとか、政治のことは一切私には仰せつけないでください」ということもできたでしょうが、そうしなかったわけです。もしかすると、そういうふうに政治向きとか何向きとか、切って分けようっていう発想自体が現代人的な発想なのかもしれません。とにかく、秀吉という自分に目をかけてくれた人に役に立てることがあるなら「別に何でもやりましょう」くらいの感じだったのかもしれないと思います。
前島: 『お茶と権力 信長・利休・秀吉』には、例えば本願寺の次期門主が大坂城に来て、利休が秀吉に代わってその案内をするという場面があります。あるいは信長に鉄砲の弾を送るとか。本当に田中さんの本を読んでいると、それも何か、おもてなしのパフォーマンスアートといいますか、広い意味での利休のお茶だったような気がします。
田中: 確かに利休は気の利く人だったと思うのですが、気の利く範囲でもお茶の話だけにとどめておこうというようには考えない。今の時代も同じだと思いますが、気が利く人は、気がついてしまったらやらざるをえないということでしょう。
前島: しかも、そこまで権力者とつき合うのは、当時の単なる社交ではなくて命がけですよね。秀吉の城を案内するということも、かなりそうした領域に入るような気がします。それは、利休だけではないかもしれません。やはり、戦国の茶人たちは、お茶を命がけの領域までやっていたのだと思いました。
田中: 自分は、いくらお茶で付き合っていただけですと言っても、「お前こいつと仲良かっただろう」と言われたら、その人が失脚すると、自分の身がどうなるかわからないということでしょうね。
お茶は、新しいルールを生み出す自由な空間

前島: また一方で、お茶は、主人と家来という関係とは違う距離感を作る一種の場でもあったのかなと思いますが、いかがでしょうか。
田中: お茶は礼儀作法の隙間に位置していたように思います。室町時代にも礼法はありますから、御殿の上だと身分の制約があり、それに従って行動をします。しかし、新しく生まれてきた文化である茶に関する礼法はまだ確立されていない。すると、茶室の中に入ると、前例がなければ何をやってもよいというような、まだルールができてない、自由な空間というものが、新しい付き合いの可能性を生み出したのではないかと思います。
前島: 付き合いの文化のルールをこれから作っていくのが、当時のお茶の本質だったという面もあるわけですね。
田中: そうですね、我々茶人の罪でもあるのですが、お茶って出来上がっていて、外れると文句言われるイメージがあるのですが、この時代は、これからルールがだんだん出来てくるという感じで、みんなが好んで人がたくさんの人がお茶をはじめるというような、そういう創成期です。
前島: その感じも、田中さんの本の中に感じ取れます。お茶の魅力を発見できる入り口になるというか。たとえば秀吉のお茶のなかにも、お茶の本質、人の心を動かすというものがあるわけですね。最初の話題に戻りますが、私はちょっとお茶っていうのは約束事がきびしくて、ちゃんと座って文句を言われながら飲むというイメージがあったのですが(笑)、そうでない部分に本質があるとわかりました。
田中: そうですね。私がこんなこと言ってはいけませんが、お茶を楽しめる人というのは、「先生こんなことやってよいのですか」と思いながらやってはいません。秀吉や信長は、絶対そうは考えなかったでしょう。俺達がお前たちを養ってやっているのだという立場だった。それぐらいの人たちだから、そこでは何か悪い意味ではなく、自分はこれをやりたいが、どうすればよいだろうという時に茶人を利用する。初めから、こういうことやったら文句言われるのではないか、みたいなことを考えない人が、お茶を本当に楽しんでいたのだと思うのです。
前島: なるほど。本来の、お茶という空間とか形式を踏まえると、それが可能になるということですね。
田中: 自分を縛るものではなく、こういうふうに先人が利用してきたソフトウェア、仕組みがあるから、それを目的に合うように利用しましょうということだと思います。
前島: 利休や秀吉たちがつくってきたパフォーマンスの空間としてのお茶という視点をふまえると、お茶を新たに楽しめる。それは歴史への興味にもつながっていく。この本を読んでは、そういうことを考えさせられました。
田中: ありがとうございました。とにかく歴史上の人物から、様々なアングルで学び、そしてお茶を楽しむことができるそんな本に仕上がっていますので、是非、ご一読いただければと思います。本日はありがとうございました。
(完)